こんにちは。フリーランス医のDr.さいとーです。
私は2021年に宅地建物取引士(宅建士)試験を受験して合格できました。
その時の勉強法などは過去記事で詳細を書いています。
今回は医師が宅建試験を受験するメリットについて記事にしました。
医師で不動産資格の取得を考えている方の参考になれば嬉しいです。
・不動産登記が自分でできるようになる
・不動産業者に騙されにくくなる
・不動産用語に強くなる
・不動産業者と対等に話せる
・受験コストが抑えられる
医師が宅建試験を受ける5つのメリット
不動産登記が自分でできるようになる
宅建で不動産登記法について勉強するので、不動産登記について基礎知識が身につきます。
その知識があれば自分で不動産登記ができるようになります。
司法書士さんに外注する費用が削減できるので、受験費用やテキスト代はすぐに回収できてしまいます。

わざわざお金と時間をかけて宅建試験を受けるのであれば、しっかり実務を身に着けて回収しましょう!

不動産業者に騙されにくくなる
宅建試験で勉強するのは民法や宅建業法など、医師が勉強した経験のない法律です。
特に民法では、悪意がある不動産行為に対して、どういう法律があるかを学べます。
医師が民法を学べば、悪徳不動産業者に騙される可能性を減らせるでしょう。

私も土地の売買契約のときに、不当な費用を払うところでしたが、宅建の知識でそれを撃退できました!
悪い業者から資産を守る防御力になっています。

不動産用語に強くなる

宅建を勉強すれば、自然に不動産用語に強くなります。
医学用語もそうであるように、不動産用語が読めるのと、意味がイメージができるというのは全く別物です。
「抵当権、市街化調整区域、再建築不可物件、用途制限、借地借家法、建築基準法・・・・」
これらの用語を理解できていなければ、不動産用語を読めても意味がありません。

不動産屋さんと話しても、私には専門用語が理解できませんでしたが、主人はよく理解できていました。宅建の勉強で不動産用語に詳しくなったおかげです!
不動産業者と対等に話せる
不動産業者と対等に話すことができるという点も大きなメリットです。
不動産仲介業者が持っている資格も宅建士資格ですから、同等の知識を持っていると言えます。
知識だけではなく、立場上も対等に話ができる点は、不動産取引において有利に働くでしょう。

私もマイホームの購入には宅建士の知識が役に立ちました!
路線価の比較や土地の吟味にはとても有用な知識でした。
不動産屋さんに物怖じしないで話せました!
受験コストが抑えられる

医師は度重なる難関試験をパスしているので、予備校などで試験対策しなくても独学で暗記が多い宅建試験にも抵抗なく臨めます。
医学以外の勉強や資格試験は新鮮でなかなか楽しく感じられるかもしれません。

朝活や仕事の合間に勉強するのは大変ではあるのですが、
仕事と勉強の両立に充実感も感じられますよ!
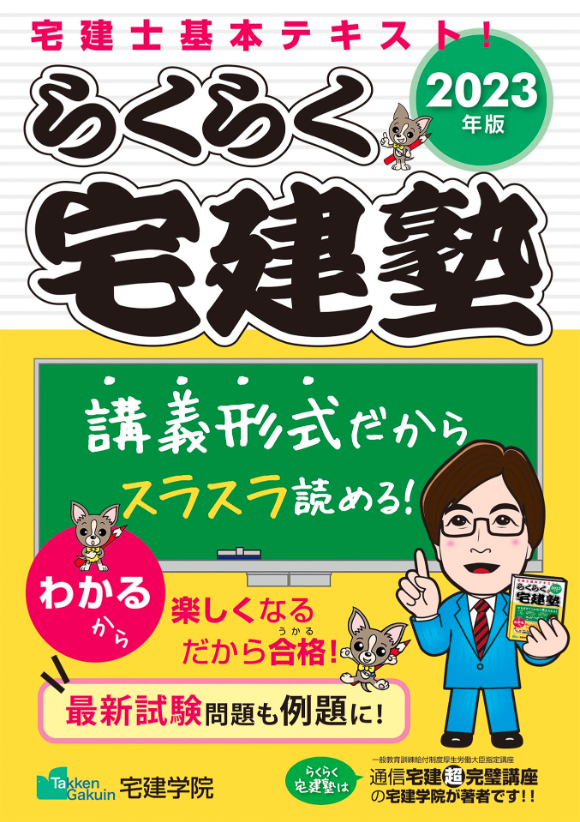
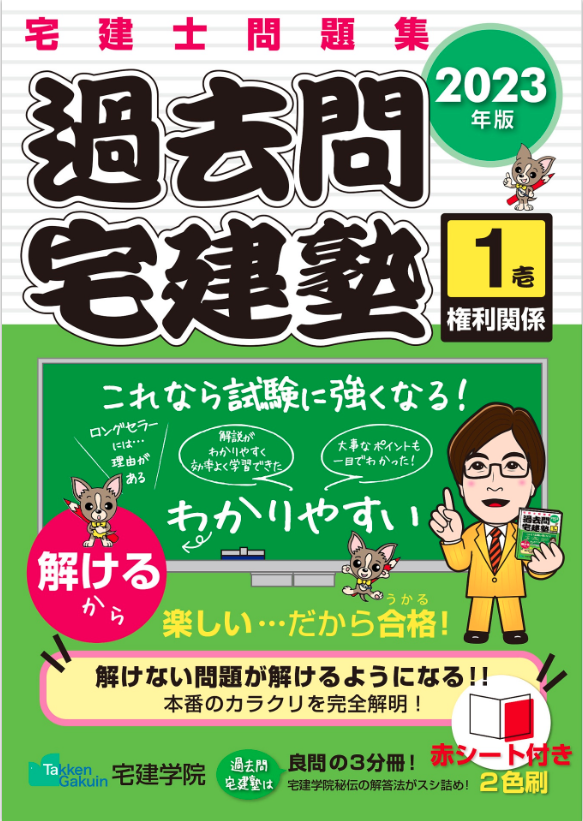
・宅建士問題集 過去問宅建塾 [2] 宅建業法 [2023年版]
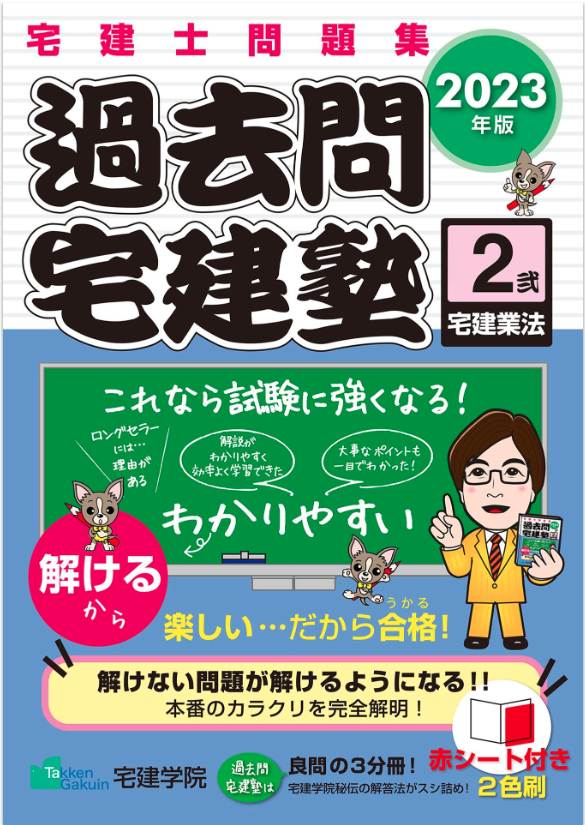
・宅建士問題集 過去問宅建塾〔3〕法令上の制限その他の分野 [2023年版]
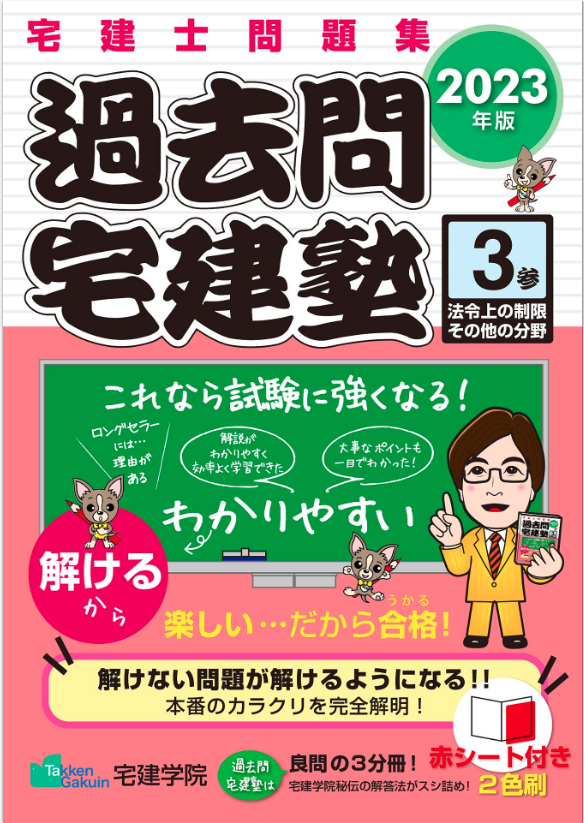

医師が宅建試験を受けるときの注意点
不動産投資の1歩目にはなりにくい
私も始めは不動産投資の事前準備として宅建試験を受験しましたが、まだ不動産投資はまだ始められていません。
確かに宅建は不動産投資の防御力の側面はありますが、投資の攻撃力が上がるわけではないように感じます。
「宅建より物件」
という格言があるように、不動産投資には不動産投資本を読み込む方が近道かもしれません。
医師が宅建試験を受けるメリットと注意点 まとめ
最後までお読みいただいてありがとうございます!
医師はその職業の性質上、不動産業者などに騙されやすい傾向があると思います。
それに対抗するにはやはり知識で武装するしかありません。
宅建試験は不動産の民法から法令などの全般知識を身につけられるので、興味のある方はトライしてみましょう!
「このブログが参考になった!!」
「ここが分からないから聞きたい!!」
という方は、関連記事の下のコメント欄にお気軽にコメントをお願いします!
以上Dr.さいとーでした!

それではまたお会いしましょう!!

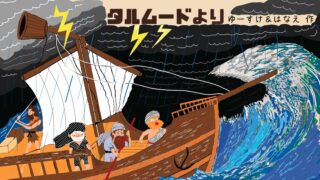
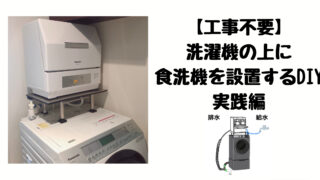








コメント
小生もとある町で消化器内科を開業している医師です。59歳にして初めて宅建試験を受け、何とか滑り込みセーフ(合格最低点は36点で、小生も36点)
で合格しました。 年齢による記憶力低下もあり、15カ月勉強し、なんとか合格にこぎつけました。宅建試験を受けようと思ったきっかけは、あらたに違う分野の勉強をすることで認知症の予防になるのではないかと考えたからです。もうすぐ60歳になろうとしていますが、記憶力は鍛えることで現状の維持を保つことができるのではないでしょうか。
バンビ様
宅建合格おめでとうございます!新たな分野の勉強は刺激的で楽しいですよね。
何歳になってもチャレンジできていて素晴らしいです!
もちろん、記憶力や脳への刺激としてポジティブな影響があると思いますよ。
私も刺激をもらって、まだまだチャレンジを続けていきたいと思います。
コメントいただき、ありがとうございました!
親子継承2代目で、糖尿病代謝内科を中心にクリニックで診察しているものです。医師17年目になります。
とりあえず、簿記2級までは取得し、少しずつ財務諸表とかを見れるように勉強していたのですが、衣食住できりはなせない「住」の資格である宅建士にはとても興味をもっています。このページにも有ります通り、すぐに税金対策のための不動産の知識を、とか不労所得のための不動産知識を、というより、まず資産形成の基礎をという認識で考えておりました。
また、取得したあと、どういう道筋があるのかなど、さいとー先生のお話などお聞きしたいな、と考えておりました。
お忙しい所もうしわけありません。失礼いたします。
つぐな様
いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。
簿記2級素晴らしいですね。
宅建は不動産の民法や登記について知識が得られるので、資産形成にとっておすすめです。
確かに、不動産投資の一歩目としては遠回り感はありますが、不動産の前提知識を得ておくことはとても有用だと思います。
実際にマイホームやクリニックの建設の知識としては大いに役立ちましたし、不動産業者の良し悪しを見極める一助にはなります。
今後の活用として、知識は不動産登記に活かして自分で登記は行っていますが、正直資格自体を活用はできていません。
ただ、宅建業者の登録後は更新が必要ですが、試験の合格自体は一生物なので、将来不動産投資を事業的規模で行う際などには活きてくる可能性はあります。
もちろん興味がお有りであれば受験をおすすめします。