こんにちは。Dr.さいとーです。
私は2021年にマイクロ法人を設立し、現在2期目です。
今回は医師がマイクロ法人するメリットを書きました。
・社会保険料を最適化できる!
・医師の所得の特徴が活かせる
・所得を分散できる
・個人の節税の幅が広がる
みなさんご存知の通り、超高齢化社会を支えるためには、高所得者層の増税は避けられません。
いわば「勤務医は増税の矢面に立たたされて、狙い撃ち状態」です。

待っていても増税の流れは変わりません!
自分の財産は自分で守らなければ!
【フリーランス医師にオススメ】医師がマイクロ法人を設立する4つのメリット
メリット1:社会保険料を最適化できる
あなたの社会保険料はいくら?
年収の約10〜13%!
勤務医のみなさんが加入する社会保険は健康保険と厚生年金、雇用保険です。
源泉徴収で天引きされていると自分の社会保険料がいくらか知らない場合もあります。
表をご覧ください。

医師のみなさんが年間支払っている社会保険料は、
年収の約10〜13%で、金額にすると年間110万円〜160万円ほどです。

医師の当直代のほとんどが社会保険料に消えるんですよね。。。(泣)
社会保険料を最適化するには
マイクロ法人で社会保険に加入すればOK
医師の医療保険は,
・勤務医→「健康保険」
・フリーランス医→「国民健康保険(国保)」または「医師国保」
です。それぞれの特徴は
・保険料が高い
・保証が手厚い(出産一時金や傷病手当あり)
・扶養家族がいても保険料は変わらない
・保険料が安い
・保証は薄い(出産一時金や傷病手当なし)
・扶養家族が増えると保険料が高くなる
つまり、健康保険と国保のイイところ取りをして保険料を安く、保証は手厚くしたい!というわけです。
社会保険料を最適化するにはマイクロ法人で社会保険に加入すればOKです。
そうすると医療保険は自社で健康保険・厚生年金に加入でき、その保険料は法人の役員報酬(標準報酬月額)で決まります。
結果的に、法人から自分への役員報酬を最低限に抑えることで、社会保険料を最低水準にできます。
マイクロ法人の節税効果は?
節税効果は年間約70万円
私が在住の地域では、最適化した保険料は個人負担分で127,188円/年(10,599円/月)でした。(同額の法人負担分あり)
勤務医時代の社会保険料が134万円だとすると
134 万 ー 12.7万 = 121.3万円
社会保険料が120万円以上、安くなりました!
ただ、社会保険料は所得控除されますので、同額が節税になるわけではありません。
所得税率33%、住民税10%として
121.3 × {1 ー (0.33 + 0.1)} ≒ 69万円
つまり、マイクロ法人を使った社会保険料の年間約70万円の社会保険料の節税ができます!

所得税率が高い医師に、マイクロ法人の活用はオススメです!
簡単3ステップ!会社設立をもっとラクに【マネーフォワード クラウド会社設立】
メリット2:医師の所得の特徴が活かせる
非常勤で安定した給与収入があること
給与所得は通常、常勤でなければ本来もらえないはずですが、医師の場合は非常勤の安定した給与所得があります。
パートタイマーのような働き方で十分な暮らしができてしまう、この特殊性には着目すべきです。
この医師の給与の特徴とマイクロ法人の強みがとても相性がいいのです。

まずは自分の転職市場を覗いてみるのはいかがでしょうか?
メリット3:所得を分散できる
家族への役員報酬や旅費交通費を出す
法人の収益を所得が少ない家族に給料を出すことで所得税の節税につながります。
私も非課税・扶養の範囲で妻に給料を出しています。
また、旅費交通費は非課税になるので、旅費交通費としての支給分の節税効果は絶大です。
法人で旅費交通費を出すには「旅費規定」を整備しましょう!
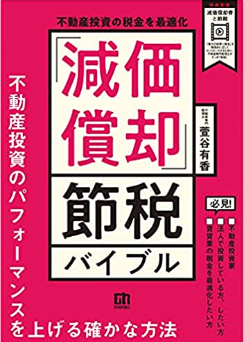
メリット4:個人の節税の幅が広がる

小規模企業共済
年間約35万円の節税をしましょう
法人役員になれば、小規模企業共済に加入できます。
最大で年間84万円の掛け金を全額所得控除できます。
年間の節税額は35万円以上と大きな節税効果があります。詳細はこちらの記事でどうぞ。
経営セーフティ共済
法人だけなく個人事業主としても加入できます
経営セーフティ共済には、継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、法人または個人事業主が加入できます。
法人で加入すれば、月々の掛け金20万円の範囲で年間240万円まで法人の損金を作れます。
少し盲点ですが、個人事業主でも加入できるので、個人の所得を減らせることも覚えて損はありません。
個人の所得を240万円減らせるのは破壊力がありますので、余剰資金があれば、加入を検討してみてはいかがでしょうか。

まー私は小規模企業共済で精一杯ですが。笑
医師がマイクロ法人を設立するの4つのメリット まとめ
これまで読んでいただきありがとうございました!
社会保険や税制の仕組みを理解し、マイクロ法人を活用することで「搾取される側」から「制度を使い倒す側」に回れます。
学んだことが資産形成や豊かな人生に繋がる可能性を大いに秘めています。
それぞれの良さを理解して、制度適切に利用していきましょう!
このブログが参考になった!という方は
という方は、関連記事の下のコメント欄にお気軽にコメントをお願いします!
以上、Dr.さいとーでした。

それではまた、お会いしましょう!!
参考書籍
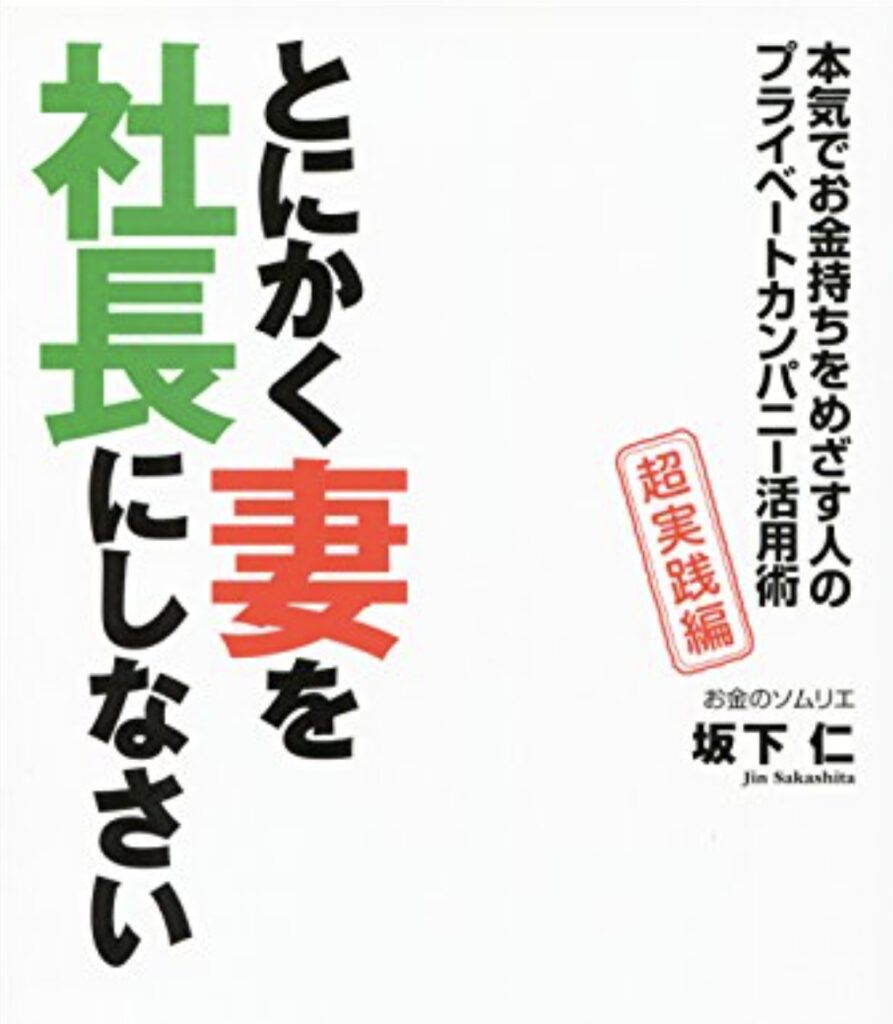
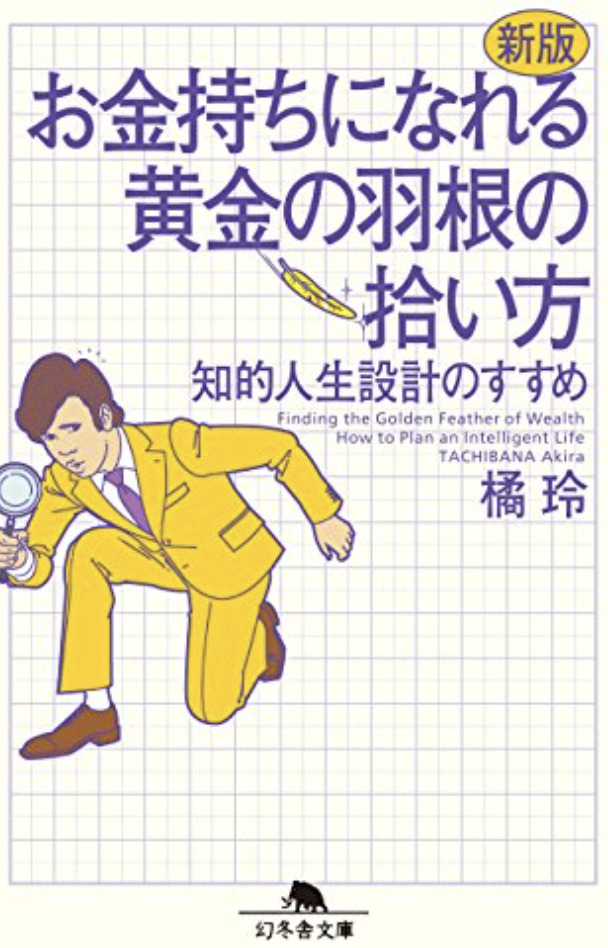
マイクロ法人のデメリットが知りたい方はこちら↓↓↓

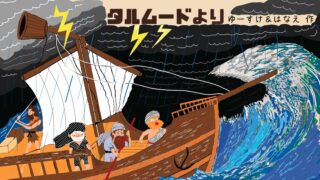
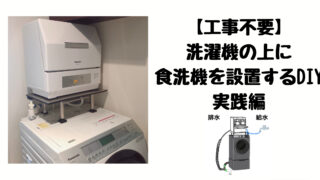









コメント
常勤で働く場合はマイクロ法人を立てても保険料は節税できず、
フリーランス医の場合にマイクロ法人立てると、保険料節税になるということでしょうか?
こんさん
コメントいただき、ありがとうございます。
常勤先を持っていると社会保険料の最適化はできないですね。
フリーランス医のように非常勤先をいくつか持っているような働き方であれば、保険料の最適化はできますね。
ただ、マイクロ法人のためにフリーランス医になるかというと本末転倒な気もします。
今後のご自身の進路や考え方次第ですね。